住まいの役割は多い。日常の中の安らぎの場、あらゆる人的活動が始まる基地、自尊心や虚栄心を満たすアイコンでもある。食物の役割は多い。身体を作る。コミュニケーションの場を作る。疲労を取り除き、回復させる。書物の役割も多い。仕事における知識を得る。ひと時の非日常が日々の生活に潤いをもたらす。

食物の最大の役割が生物としての命をつなぐことであれば、書物の最大の役割は、智恵と経験を後の命へつなぐことであると思う。昭和45年に記された吉村昭 著「三陸海岸大津波」(文春文庫)には、著者の後世へ向けたそんな意思が詰まっている。歴史は繰り返し、人はそれを忘れる。未来は読めないから、過去に学ばねばならない。というよりも過去に学ぶより他に方法が無い。不動産、住宅を生業とする者として、この書物は住まいの役割が命を守るシェルターであり、時代を繋ぐ生物の巣であることを突き付ける。

住宅を購入するときに必ず押さえておきたい、ハザードマップ。後述の三陸海岸に始まり、熊本城も破壊した地震、鬼怒川や千曲川の決壊。洪水に見舞われ、床上浸水被害に遭った現場をその都度ハザードマップと照らし合わせるのだが、かなりの高確率で一致する。この意味においては政治行政は一定の役割を果たしていると私は思う。ただ、そら恐ろしく感じてしまうほど、急傾斜区域、崖の真下、高台と高台の間を流れる河川の脇に、住宅街が形成されている。タワーマンションは言うに及ばずなのだが、経済的であることと利便性に優先順位を置き過ぎていると感じている。被害者を揶揄するつもりは決して無いし、かく言う私の自宅の位置も絶対安全な場所ではないのだが、自然災害に被災した住民がTVカメラに異口同音に話す、「私がここに住んで〇〇年だけど、こんなことは無かった」という感想に、シェルターとしての住まいの危機管理についていつも考える。

本の中で、「三陸沿岸を襲った津波は数知れない。主だったものだけでも…」歴史には18回の津波が記されていると吉田氏は記す。比較的新しいもので、明治29年の津波の死者は26,360人、昭和8年2,995人、昭和35年105人。凄まじい被害を受けている。と同時に、この被害の激減について吉田氏は住民の津波に対する認識の高まり、防潮堤その他の備えの充実を理由に挙げている。

そして、東日本大震災の死者は令和3年3月9日時点で15,899人(警察庁発表)である。2011年3月11に発生した東日本大震災に伴う津波の発生も、90%以上の確率と予見していたと聞く。歴史に学ばなかったから甚大な被害が生じた、などという単純で無遠慮な話はしない。良質な漁場=職場である海岸へのアクセスもあったろう。地域の空気感も、死生観も絡んでこよう。なぜそんな危険な場所に住まいを構えたのか、という話は、拡大すれば『日本沈没』につながる、世界の震度7以上の地震が30%以上集まる日本になぜ住むのかまでつながっていく。都市ではなく不動産市場という感覚の薄い地方に住む者にとって、住む場所ということは都市に比べて数倍選びにくいとも思う。
2021年末現在、京都大学名誉教授の鎌田氏によれば、2030年代に70~80%の確率で南海トラフ地震が起き、富士山の噴火も心配されるという。予測値では30万人が亡くなり、噴火が起きて2cm火山灰が積もれば、首都機能は完全に麻痺すると予想されている。
本書から私が考えるのは、中長期的な、ビジネスで言うところの「急ぎではないが重要な仕事」についての行政の役割である。コロナ禍でも幾度となく取りざたされた「私有権」にもからむ問題である。現在の日本において、この私有権はプライバシー配慮・個人情報保護を隠れ蓑にした、無責任から来る無作為に見える。コロナであれ、津波であれ、本当に国民の生命を守ろうとするのであれば、「いいから今は、この場面では、生きていくために言うことを聞いてくれ」という政治家の言葉は無いのだろうか。「私が責任を取るから」と。

コロナ対応や経済格差を見て、欧米諸国が日本より勝っているとは私は思わない。しかしながら住宅政策を聞くと、政策に意思について、彼我に大きな差を感じる。アメリカ・シリコンバレーでは、深刻な住宅不足にも関わらず、日本人の目から見たところの空き地が無数にある。しかし開拓させない。無制限の開拓は危険地帯へつながることもあり、また既存の土地の価値を下げてしまうという至極まともな価値がある。フランスでは行政が強力な力を持ち、その地域にそぐわないデザインの建物を、「そんなダサいものは建てたら町の価値が落ちる」という理由で行政官の裁量で認可を下ろさないそうである。良し悪しはともかく、行政に「この国と地域をこうしていく」という意思がある。
「今は日本国の存続のために私の言うことを聞いてくれ」と必死で説かんがための演説をコロナ禍で聞けなかったように、本書をはじめとする歴史書に学んだ官僚が、政治家が「日本国土には、住むべき場所とそうでない場所がある」と必死で考え、説いた結果の都市計画には見えない。「我々はそこはちょっと危険ですよ、ってハザードマップを使って言ってますよね。あとはご自由に」という態度が、多数の死者と住宅被害を生んではいないか。
政治が悪い、という話は「政治が良かった時代などない」と常に完結する。日本の都市計画も、建築基準法も、災害対策基本法(もおそらく)も、我々一般人を守ってくれるようにはできていない。ありがたくも自衛隊は助けてくれるかも知れないが、自分の身は自分で守る。自分の家族や財産は自分で守る。自分の地域は地域の大人が守る。できることなら政治に最も活躍してもらいたい危機管理だが、日本ではそれを望めそうにない。
本書の最後に昭和43年の津波を経験した方がこう結んでいる。「津波は今後も必ず襲ってくるが、色んな方法で警戒しているから、死ぬ人は滅多にないと思う」。ごめんなさい吉田さん、我々は学べていないようです。だから、「我が身は自分で守る」ための住宅知識を身に付けねばならない。それを世の中にも提供していかなければいけないと、この本を読んだ私は思う。ほんの少しでも、吉田さんの遺志を受け継ぎたいと願うところである。






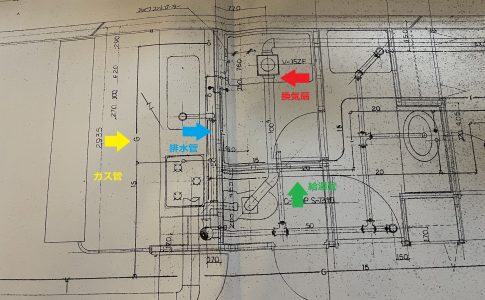
コメントを残す